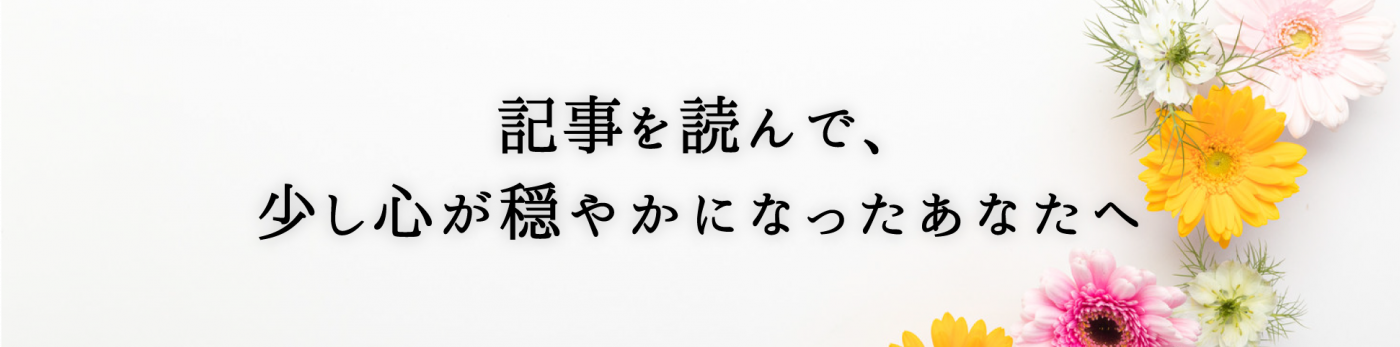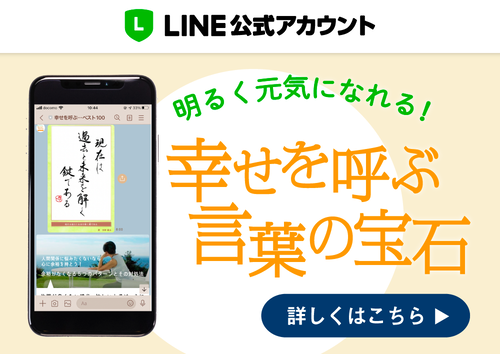妻の束縛が辛すぎて家出した皇帝がいる?|束縛の強さは愛の深さか(後)

こんにちは、暮らしを良くする研究家のこんぎつねです。
前回の記事妻の束縛が辛すぎて家出した皇帝がいる?|束縛の強さは愛の深さか(前)では隋の皇帝・楊堅(ようけん)が妻である伽羅(から)の束縛が辛くて家出したエピソードを紹介しました。
夫婦関係に重きを置き、夫を束縛する伽羅の考えは果たして正解だったのでしょうか。
夫以外にも厳しかった伽羅
伽羅の妻を大事にしない男性に対する厳しい目は楊堅以外にも向けられました。
長男の楊勇(ようゆう)は勉強ができて、詩を作るのも上手く、性格も寛大かつ温厚な人柄だったのですが、多くの側室を持ち、正妻よりも側室を大事にしたので伽羅(から)は嫌っていました。
これを知った次男の楊広(ようこう)は側室を持たずに正妻だけを大切にしているフリをし、楊広の家を楊堅と伽羅が訪ねるときはわざと装飾を質素なものに代え、側室を別室に隠し、楽器にほこりをかけて使われていないように見せました。
質素好きな楊堅と伽羅は
「楊広は派手なことが嫌いで質素を好む子なんだ」
と喜んで5人の息子の中でも一番かわいがるようになり、やがて楊広と仲のいい家臣や伽羅からの勧めもあって、楊勇は次期皇帝の座から降ろされて楊広(ようこう)が皇太子になりました。
このように夫だけではなく息子や家臣に対しても女性に関する束縛のきつかった伽羅(から)は602年、49歳で亡くなりました。
伽羅が死んだ後の楊堅(ようけん)は今までの束縛の反動からか62歳にして後宮に入り浸るようになりました。
特に宣華夫人(せんかふじん)という女性をかわいがるのですが、後宮に入り浸り過ぎたせいかすぐに病気になり
「伽羅の言う通りにしとけばよかった…」
と後悔したのでした。
伽羅の言う通りにしておけば病気にならなかったでしょうが、そもそも伽羅の束縛がきつくなければこんなことにはならなかったかもしれません。
楊堅の最期と煬帝の即位
604年、伽羅が死んで2年後の7月に楊堅(ようけん)は重体となりました。
病床で寝ていると、看病をしていた側室の宣華夫人(せんかふじん)が泣きながら寝室に駆け込んできます。
楊堅「宣華よ、どうした?」
宣華夫人「楊広様に乱暴されそうになりました!」
楊堅「なんだとっ、おのれ楊広の畜生め。今までワシをだましておったな!あいつに後を継がせてなるものか!伽羅がワシを誤らせたのだ!」
楊広(ようこう)の本性を知った楊堅は怒って、長男の楊勇(ようゆう)を呼ぶように家臣に命じました。
しかしその家臣は楊広の息のかかった者だったため、このことを楊広に報告してしまいます。
楊広「ふーん、兄上を呼べとねえ。おい張衡(ちょうこう)、ゴニョゴニョ」
張衡「はい、かしこまりました」
張衡は楊堅が寝ている部屋に向かい、夫人や侍従を別室に離れさせ、“なぜか”その直後に楊堅は亡くなりました。(この話は楊広を親殺しの悪人に見せるための唐の時代の作り話という説もあります)
こうして楊広は跡を継いで604年に隋の2代目皇帝となったのです。
楊広の治世
楊広は皇帝になるや倹約生活が打って変わって派手な生活をするようになりました。
また邪魔な兄の楊勇を10人の息子ともども死なせ、謀反を起こした弟の楊諒(ようりょう)を破って庶人に落としました。
楊堅(ようけん)は生前に
「過去の皇帝たちは多くの女性との間に子供を作ったから、その子供たちが後継者争いをして国が滅んだ。しかしワシの息子はみな同じ母親から産まれたからそんな心配は無用だ」
と言っていましたが、同じ母から産まれた子供どうしでも結局争いになってしまいました。
さらに楊広は様々な政策を進めます。
- 中国を縦断する2500kmの大運河の建設
- 万里の長城の修復
- 高句麗遠征
などを急ピッチで行い、国は疲弊し、国民は恨みを募らせていきました。
女性を含む100万人を動員して掘削された大運河は現在でも京杭大運河(けいこうだいうんが)として残っており、歴代王朝で大いに活用されて、2014年には世界遺産になっていますが、当時の人たちにとっては大変な労役でした。
また豪華な祝宴を何度も行ったり、観光であちこちに行ったりしたことも財政を厳しくさせました。
そして大規模な高句麗遠征を3度行いますがすべて失敗。
これらの圧政に耐えかねて各地で反乱がおこり、対処ができなくなったため今まで住んでいた長安を離れて江都(江蘇省揚州市)に逃げましたが、そこで部下の反乱により最期を遂げました。
その後、楊広の死を聞いた李淵(りえん)が楊広の孫の楊侑(ようゆう)から禅譲を受けて新たに唐を建てたため、300年ぶりに中国統一を果たした隋はわずか2代37年で滅亡しました。

楊広が造らせた京杭大運河
隋の時代が与えた影響
楊広は中国史上でも屈指の暴君とされますが、それは唐の時代に書かれた歴史書が後世に伝わったため悪く描かれている面もあります。
隋は後の時代に大きな影響を与えています。
大運河は前述の通り現在まで使われ、経済の中心だった南方と政治・文化の中心だった北方を結びつけて中国全体を発展させるのになくてはならないものでした。
科挙制度も隋代から1904年までずっと使われ続けます。
また、楊堅も伽羅も楊広も熱心な仏教信奉者で、楊堅は長安の都に大興善寺という大きな寺を作ったり、僧尼を保護して3800寺近くの寺院を建立して仏教を中国全土に広めています。
これらの寺院は後に日本の国分寺の起源となりました。
楊広は中国天台宗を開いた智顗(ちぎ:天台大師とも言う)に帰依し、菩薩戒を受け「總持」の法名を受けています。
一方で智顗に対しては「智者」の号を与えました。
このような背景があって、他にも隋の時代には多くの宗派や有名な僧侶が生まれています。
楊堅に招待されて大興善寺で講釈した地論宗・浄影寺の慧遠(えおん)や、楊広の命令で揚州の慧日道場や長安の日厳寺などで講釈した三論宗の吉蔵(きちぞう:嘉祥大師(かしょうだいし)とも)などが有名です。
日本に影響を与えた宗派で言えば、609年、楊広の治世下で道綽禅師(どうしゃくぜんじ)が浄土教を起こし、その弟子の善導大師(ぜんどうだいし)が浄土教を大成しました。
善導大師の書いた観無量寿経疏(かんむりょうじゅきょうしょ)はその後日本に伝来し、それを学んだ法然(ほうねん)上人が日本で浄土教を伝え、弟子の親鸞(しんらん)聖人が浄土真宗を広めました。
現代の日本には浄土真宗の家庭が多いですが、たどれば隋の時代に行き着くのです。
楊堅、楊広が仏教を保護しなければ、浄土真宗が日本に広まることはなかったかもしれません。
まとめ
妻の束縛が辛いと嘆く旦那さんは今も昔も変わりません。
それは
「私たちの子供が一人前になるまで子供と私の面倒を見てほしい」
という女性の願いから来るものですから、
- 花を渡す
- 「いつもありがとう」と言う
- 手を握る
- 抱きしめる
- 時間をかけて何かを用意する
- 一緒に作業をする
などをすると奥さんの束縛も緩まるかもしれません。
隋の皇帝楊堅(ようけん)の奥さんの伽羅(から)も夫を束縛するタイプの女性でした。
その性格を逆手に取った次男の楊広(ようこう)は正妻を大事にする素振りで皇太子になります。
楊堅が死ぬと楊広は隋の2代目皇帝になりますが、失策が続いて部下に反乱を起こされてあえなく最期を迎えます。
しかし隋の時代に保護された仏教は後の中国、そして日本に大きな影響を与えました。
こんぎつね
最新記事 by こんぎつね (全て見る)
- ギブアンドギブの意味は?|ギブアンドテイクよりギブアンドギブを! - 2025年6月18日
- 「あの人大嫌い!」そんな人は永遠に敵なの?|敵を味方にする方法 - 2021年1月4日
- 左遷されても諦めないで|左遷先で歴史に名を残した司馬光に学ぶ(後) - 2018年11月8日